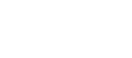
| 排水量 | 常備 15,140t, 満載 15,179t |
|---|---|
| 長さ | 水線長 126.5m, 全長 131.7m |
| 全幅 | 23.2m |
| 喫水 | 8.28m |
| 機関 | 2軸レシプロ, 15,000ihp |
| 燃料 | 石炭 1521t |
| 速力 | 18ノット |
| 装甲 | 水線帯 100-230mm, 上部水線帯 150mm, 甲板 50-75mm, バーベット 200-360mm, ケースメイト 50-150mm |
| 兵装 | 30cm砲 連装2基 4門, 15.2cm砲 単装14基 14門, 12ポンド砲 単装20基 20門, 3ポンド砲 単装8基 8門, 4.5ポンド砲 単装4基 4門, 45cm魚雷発射管 4門 |
| 乗員 | 830 |
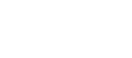
| 艦名 | 計画 | 建造 | 起工 | 進水 | 竣工 | 本籍 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三笠 | Mikasa | 明30 | 英 Vickers | 1899. 1.24 | 1900.11. 8 | 1902. 3. 1 | 舞鶴 | 一等戦艦 | 1905. 9.11 事故着底(佐世保) 1905.12.12 戦艦 1906. 8. 8 救難浮揚 1921. 9. 1 一等海防艦 1921. 9.16 座礁(ロシア沿海州) 1923. 9.20 除籍 1923.10.11 着底(横須賀) 1926.11.12 記念艦 |